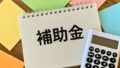中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者が連帯保証人となり、信用補完を行うことは、これまで一般的な慣行とされてきました。
しかし、経営者保証はもう“当たり前”ではありません。
この記事では、経営者保証を解除するための実践的なアプローチを、「ガイドライン」に基づいて解説します。特に重要な「3つの条件」と、金融機関との正しい交渉術を押さえることで、あなたの会社も保証解除に一歩近づけます。

経営者保証に関するガイドラインの位置づけ
経営者保証に依存しない融資の推進については、2013年に日本商工会議所と全国銀行協会が事務局となって「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
さらに、2022年12月には、金融庁が経済産業省・財務省と連携し、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を一層加速させるため、「経営者保証改革プログラム」を策定しました。
これに伴い、内閣総理大臣をはじめ、財務大臣、金融担当大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣の連名で、「『経営者保証に関するガイドライン』の内容を十分に理解し、適切な対応を行うこと」との要請文も発表されています。
このように、経営者保証に依存しない融資慣行の確立は着実に進展しています。
「経営者保証に関するガイドライン」は法的拘束力を持つものではなく、最終的な判断は金融機関に委ねられているものの、もはや無視できない社会的規範となりつつあります。
経営者保証はなぜ外れないのか?
前述のとおり、国は金融機関に対して、経営者保証に依存しない融資の実現を強く求めています。
しかし、中小企業に対する融資の実情を見てみると、依然として融資の際には経営者保証が求められるケースが多く見られます。その一因として、中小企業の経営者が「経営者保証に関するガイドライン」の内容を十分に把握していないことが挙げられます。
同ガイドラインは全体で13ページですが、一般の債務者に関わる重要な部分はわずか2ページ程度であり、融資に明るくない方であっても十分に内容を理解することができます。
経営者保証を解除するための3つの条件【ガイドラインの正しい使い方】
経営者保証を外すためには、「経営者保証に関するガイドライン」に沿って、所定の条件を満たす必要があります。
単に「連帯保証人になりたくない」と主張しても、条件を満たしていなければ、金融機関に取り合ってもらうことは難しいのが現状です。
ガイドラインでは、債務者(経営者)に対し、以下の3つの要件を「努力義務」として求めています。
- 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
- 財務基盤の強化
- 財務状況の正確な把握、経営の透明性確保
参考:経営者保証のガイドラインP4~P5一部抜粋(主たる債務者及び保証人における対応)
主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められる。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。また、こうした整備・運用の状況について、外部専門家(公認会計士、税理士等をいう。以下同じ。)による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましい。
② 財務基盤の強化
経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。
なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。
経営者保証のガイドラインP4~P5一部抜粋
以下では「経営者保証のガイドライン」に記載されている3つのポイントを根拠を示しながら更に深堀をしてご紹介します。
法人と経営者との関係の明確な区分・分離
多くの中小企業では「会社のお金」=「社長のお金」のような状態となってしまいます。しかし、この状態ではガイドラインが求めている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」となりません。
明確な区分の基準は令和4年6月30日に発表された「ガイドラインに関するQ&A」に例示がされています。
例えば、
- 自宅兼事務所の解消
- 自家用車兼営業車の分離
- 個人の家事費用の明確な線引き
1・2については明確な分離が難しい場合には法人から経営者に適正な賃料を支払うことにより対応します。
また、3については「中小企業の会計に関する基本要領」等に則った信頼性のある計算書類の作成し、金融機関へ定期的に報告を行うや専門家の検証などが望ましいとされています。
参考:令和4年6月30日 「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(Q4-1) 一部抜粋
経営者保証を提供することなしに資金調達を希望する場合、主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努めることが求められていますが、具体的に主たる債務者や経営者はどのように対応すればよいのでしょうか。
A.法人の事業用資産の経営者個人所有の解消や法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止等、法人の資産・経理と経営者の資産・家計を適切に分離することが求められます。例えば以下のような対応が想定されます。
資産の分離については、経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、経営者の都合によるこれらの資産の第三者への売却や担保提供等により事業継続に支障を来す恐れがあるため、そのような資産については経営者の個人所有とはせず、法人所有とすることが望ましいと考えられます。なお、経営者が所有する法人の事業活動に必要な資産が法人の資金調達のために担保提供されていたり、契約において資産処分が制限されているなど、経営者の都合による売却等が制限されている場合や、自宅が店舗を兼ねている、自家用車が営業車を兼ねているなど、明確な分離が困難な場合においては、法人が経営者に適切な賃料を支払うことで、実質的に法人と個人が分離しているものと考えられます。
経理・家計の分離については、事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付は行わない、個人として消費した費用(飲食代等)について法人の経費処理としないなどの対応が考えられます。
なお、上記のような対応を確保・継続する手段として、取締役会の適切な牽制機能の発揮や、会計参与の設置、外部を含めた監査体制の確立等による社内管理体制の整備や、法人の経理の透明性向上の手段として、「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った信頼性のある計算書類の作成や対象債権者に対する財務情報の定期的な報告等が考えられます。
また、こうした対応状況についての公認会計士や税理士、弁護士等の外部専門家による検証の実施と、対象債権者に対する検証結果の適切な開示がなされることが望ましいと考えられます。
財務基盤の強化
経営者保証を外すためには、会社の収益力のみで融資の返済が滞りなく行えることが前提となります。
そのためには、業績が安定しており、融資返済に十分なキャッシュフローが確保されていることが重要です。
また、一定の内部留保が蓄積されていることが求められ、加えて今後も安定した業績が見込まれることが重要な要素となります。
参考:令和4年6月30日 「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(Q4-5) 一部抜粋
「財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する」とありますが、具体的にはどのような財務状況が期待されているのでしょうか。
A.経営者個人の資産を債権保全の手段として確保しなくても、法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況が期待されています。例えば、以下のような状況が考えられます。
業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分であること
業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断し得ること
内部留保は潤沢とは言えないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高いこと
財務状況の正確な把握、経営の透明性確保
ガイドラインでは、会社は金融機関などに対し、貸借対照表や損益計算書などの財産状況が分かるものに加え、事業計画や業績見通しなどを開示し、説明することにより経営の透明性を確保することが求められています。
参考:令和4年6月30日 「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(Q4-7) 一部抜粋
「正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する」とありますが、具体的にどのような対応が求められるのでしょうか
A.対象債権者の求めに応じて、融資判断において必要な情報の開示・説明が求められます。例えば、以下のような対応が求められます。
貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定明細(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)の提出
期中の財務状況を確認するため、年に1回の本決算の報告のみでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告
「経営者ガイドライン」「経営者保証改革プログラム」が利用されている制度
東京都の信用保証協会の基準(金融機関連携型)
保証協会は「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、平成30年4月1日から、経営者保証を不要とする制度を設けています。
以下はそのうち最も使い勝手がよいと思われる「金融機関連携型」が適用される要件です。
【金融機関連携型の適用要件】
取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、「財務要件」を満たすほか法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。
財務要件とは以下の2つを満たすこと
- 直近決算期において債務超過でないこと
- 直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
日本政策金融公庫の経営者保証免除特例制度
日本政策金融公庫においてもガイドラインを受けて経営者保証を免除する制度があります。
以下は「日本政策金融公庫の経営者保証免除特例制度」の要件です。
次の1から7までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
- 税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。
(2)公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は、取引状況に問題がないこと。
(3)次のいずれかの要件を満たす方
ア 最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
イ 直近の決算期において債務超過となっていないこと
- 物的担保の提供がある方であって、前1(1)の要件を満たす方
- 新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方で、かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等であって、前1(1)および(2)の要件を満たす方
- 取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方
- 事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方
- 新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方
- ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方
経営者保証を外すための流れ
経営者保証はガイドラインに記載している上記要件を満たせば自然に外れるわけではありません。
金融機関等へ積極的に経営者保証の解除の打診を行動として起こすことが重要です。
以下では経営者保証を外すための手順を紹介します。
金融機関に正面から頼んでみる
まずは、素直に金融機関に対して「経営者保証を外したい」と相談してみましょう。
その時点で、ガイドラインが示す要件を満たしていれば、経営者保証を外してもらえる可能性もあります。
仮に外すことが難しい場合でも、その理由や障害となっている要因を金融機関へ確認することが重要です。
課題が明確になれば、今後どのような改善が必要か見えてきます。
条件をクリアする
経営者保証を外せない場合には、「経営者保証に関するガイドライン」のいずれかの要件を満たしていないことが原因であると考えられます。
まずは、そのネックとなっている要因を明確にし、該当部分の改善に取り組むことが重要です。
たとえば、「個人と法人の明確な区分」が課題となっている場合は、比較的短期間で対応できるケースが多い一方で、「財務内容」が問題となっている場合には、要件を満たすまでに一定の時間を要する傾向があります。
なお、経営者保証を外すための要件は、すべての金融機関が同一のガイドラインを基準としているため、複数の金融機関と取引がある場合でも、基本的には同様の対応が求められます。
専門家に相談することも必要
経営者保証を外すためには、財務諸表の信頼性も重要な要素となります。
その信頼性を確保するためには、「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠した財務諸表を作成し、併せて「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」の作成を、顧問税理士に依頼することも有効な手段の一つです。
ガイドラインにおいても、専門家の支援や「中小企業の会計に関する基本要領」への言及がなされており、こうした取り組みは経営者保証を外すための有効な方法といえるでしょう。
まとめ
中小企業の融資において経営者が連帯保証人となる慣行は一般的でしたが、政府は「経営者保証に関するガイドライン」や「経営者保証改革プログラム」に基づき、金融機関に対し個人保証解除の検討を促しています。
経営者保証を外すためには、ガイドラインに定められた3つの要件を満たす必要があります。
経営者保証解除のための3要件
- 法人と経営者の明確な区分・分離
自宅兼事務所や営業車の使用区分など、法人資産と個人資産の明確な分離が求められます。 - 財務基盤の強化
会社の収益力のみで返済が可能であること。内部留保やキャッシュフローが十分である必要があります。 - 経営の透明性確保
試算表や資金繰り表を含む定期的な財務情報の開示と説明責任が必要です。
これらを満たしたうえで、まずは金融機関に保証解除を正式に依頼することが重要です。また、必要に応じて専門家の助言を受け、財務書類の信頼性を高めることで解除の実現に近づきます。
ひらい税理士事務所 代表税理士
埼玉県越谷市・草加市を中心とした近隣地域において、地域密着型の税理士として活動。
地域金融機関や関連他士業等とのネットワークを活かし、法人決算業務にとどまらず、資金繰り・融資支援、税務調査対応、相続税・資産税業務など、経営者の幅広いニーズに対応。これまで多くの税務調査に立ち会ってきた経験と、金融機関を意識した決算・申告書作成には定評があり、経営の安定と将来の発展を見据えた実践的なサポートを行っている。