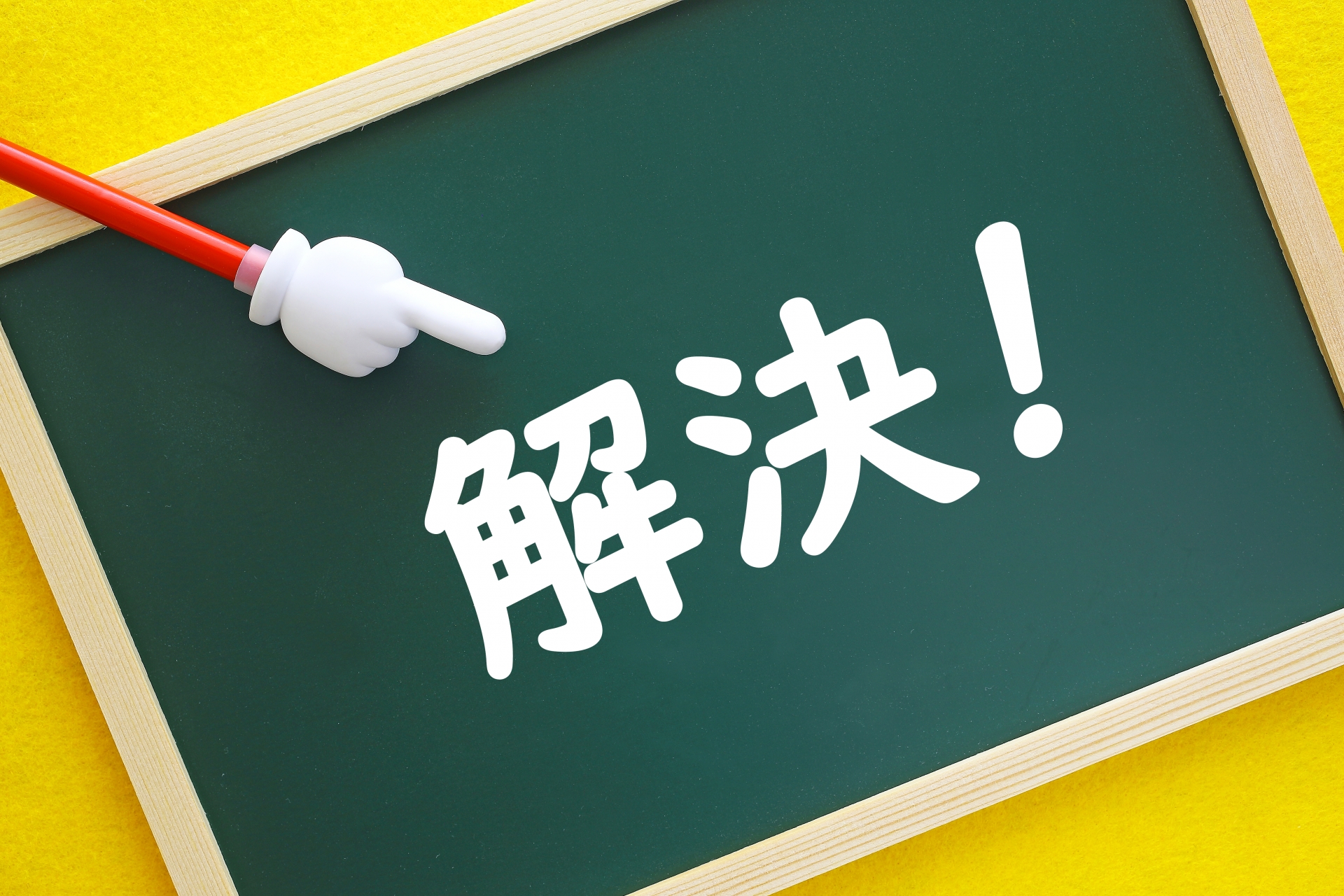毎年3月にやってくる「確定申告」。
給与所得者(会社員)であっても、医療費控除やふるさと納税、株取引、仮想通貨、事業所得、アルバイト・フリーランス収入などがあれば、確定申告が必要になる場合があります。
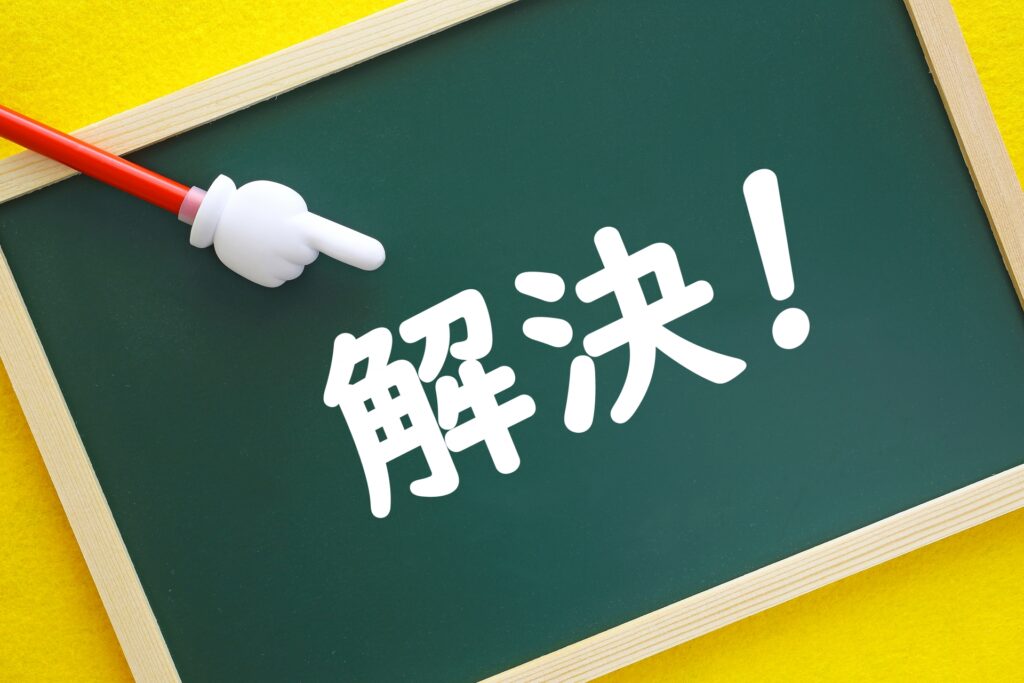
しかし実際には、確定申告すべき人の中に「確定申告していない」人が相当数いるのが現実です。
今回は、確定申告していない人がどの程度いるのか、なぜ多いのか、その背景とリスク、確定申告を行うメリットについてわかりやすく解説します。
確定申告していない人はどれくらいいる?無申告者への調査動向は?
令和6年11月発表の国税庁のデータ(令和5年事務年度)によると、
実地調査と簡易な接触を合わせた調査等を行った約60万5千件のうち約半数の31万1千件が申告漏れが見つかりました。また無申告者に対する調査件数は所得税は5274件、消費税は7827件が実施されました。
| 事業年度 | 所得税 無申告調査件数 | 1件あたり 申告漏れ所得金額 | 1件あたりの 追徴税額 | 消費税 無申告調査件数 |
| 令和5年事業年度 | 5274件 | 2590万円 | 417万円 | 7827件 |
| 令和4年事業年度 | 5229件 | 2711万円 | 429万円 | 7615件 |
| 令和3年事業年度 | 3828件 | 2923万円 | 497万円 | 5257件 |
| 令和2年事業年度 | 2993件 | 2565万円 | 292万円 | 3294件 |
| 令和1年事業年度 | 7328件 | 2160万円 | 237万円 | 8329件 |
| 平成30年事業年度 | 8147件 | 1662万円 | 242万円 | 9631件 |
| 平成29年事業年度 | 7779件 | 1662万円 | 207万円 | 9400件 |
| 平成28年事業年度 | 7612件 | 1406万円 | 146万円 | 8816件 |
上記の表は国税庁発表の各事業年度 所得税及び消費税調査等の状況より当税理士事務所が集計したものです。
コロナにより調査件数は減少していましたが最近では調査件数は徐々に回復し、マイナンバーの普及、インボイスの導入など無申告者の把握が確実に進んでおり、1件あたりの追徴税額も多くなっていることから以前に増して無申告者への調査が厳しくなっていると考えられます。
なぜ確定申告していない人が多いのか?
これまで数多くの税務調査に立ち会う中で、無申告の方々と直接お話しする機会がありました。
その中で見えてきたのは、「悪意があって確定申告していない」というケースは実は少なく、多くの場合、制度に対する誤解や不安、知識不足が背景にあるという現実です。
以下では、実際の体験談も交えながら、無申告になってしまう理由をご紹介します。
「自分は確定申告しなくてよい」と思い込んでいる人が多い
会社員の人が「給与は源泉徴収されているから関係ない」と思っていても、以下のようなケースでは確定申告が必要です。
- 年収が2,000万円を超える
- 給与の他に副収入がある(事業・アルバイト・株・仮想通貨など)
- 2か所以上から給与を受け取っている
- 医療費が10万円を超えた
- 寄付や住宅ローン控除などを使いたい
これらは、意識していないと見落としやすいポイントです。
確定申告が面倒・手続きがよくわからないと思っている人が多い
申告のための帳簿付けやレシート管理、書類の提出などが面倒で後回しにしてしまい、結果的に期限を過ぎる人も多いです。
また、「e-Taxが難しそう」「マイナンバーカードが必要?」「どこまで経費にできるの?」など、知識不足が申告遅れや無申告につながることもあります。
確定申告していなくても金額が少ないからバレないと思っている人が多い
「少額の収入だから申告しなくてもバレないだろう」と考える人もいます。
しかし、税務署は各種データ(支払調書、銀行振込、マイナンバー、証券口座など)を元に情報を把握しているため、少額でも把握されている可能性があります。
確定申告していないのは故意ではなく単に忘れてしまっている人が多い
確定申告を故意にしないのではなく、単に忘れてしまっている人も少なくありません。
申告の必要性を理解していても、仕事の忙しさや体調不良、家庭の事情などで、つい申告期限を過ぎてしまうことがあります。
また、申告を後回しにした結果、そのまま数年が経過し、申告が必要だったこと自体を忘れてしまうケースもあります。
確定申告していなければ副業が職場にばれないと思っている人が多い
本業の職場が「副業禁止」の場合、副業が発覚することを恐れて、確定申告をしない人もいます。
特に住民税の通知から副業が知られる可能性があるため、申告書の書き方がわからずに確定申告を避けてしまう場合があるようです。
確定申告しないことで脱税となる恐れがあり、逆にリスクが高まります。
納税資金がなく、確定申告を行うと納められずに差し押さえにあうと思っている人が多い
納税資金が手元にないため、確定申告を行うとすぐに税金を請求され、支払えずに財産を差し押さえられるのではないかと不安に感じ、申告をためらう人は少なくありません。
さらに、「どうせ払えないのだから」と気持ちが沈み、確定申告そのものが憂鬱で手につかないという人もいます。
実際に確定申告していなかった人たちの事例

株式の譲渡を特定口座で行っていた。源泉徴収をされているものと思い確定申告は不要と考えていたが、実際には口座の設定が源泉徴収なしになっており、後日、税務調査に発展した。

個人事業主で建設業を営んでいたが、「収入」「所得」という言葉の意味がよく理解できずに収入の金額を利益と勘違いしていた。数年後、売上の計上漏れを疑われて税務調査に発展。

個人事業主で美容業を営んでおり、創業初年度に確定申告が必要と思い税務署へ相談。その際、初年度で所得が出ていなかったことから申告不要と言われた。税務に関する知識不足から、その結論だけを覚えてしまい、自分は確定申告不要だと勘違い。10年経過後に税務調査が実施された。初年度に言われたことをずっと信じていたが数年後には所得が発生しており、資料も廃棄していたため推計課税での申告となってしまい多額の税負担が発生。

生命保険の満期返戻金が入り、随分昔に掛けたものだし、金額も多くはないからと確定申告を行わなかった。後日、税務署から一時所得漏れを指摘され、夫の扶養から外れ、追徴課税が発生。夫の会社にも迷惑をかけることになってしまった。

引っ越しで資料を紛失してしまい確定申告が出来ない状態に。その後、仕事が忙しくなり申告期間が終了。申告することすら忘れてしまった。後日、税務署から連絡があり無申告加算税と延滞税を負担することに。

副業禁止の会社で小遣い稼ぎのため、ライバーとして活動。源泉徴収もされているし、確定申告をすると職場にバレてしまうと考えて無申告状態を放置。数年後に税務調査が実施された。

個人事業主のAさんは事業自体は順調だったが、子どもが4人おり扶養家族が多かった。上は大学生、下は中学生で、教育費や食費が最もかかる時期だったため、余裕資金はほとんどなかった。確定申告は奥さんが担当していたが、「申告すると学費が払えなくなるのでは」といった強い不安があり、どうしても申告できない状態が続いた。数年が経過した後に税務調査に移行。無申告が続いたため青色申告は取り消され、専従者給与も認められず、多額の税負担が発生した。
確定申告しないと、どんなリスクがある?
確定申告すべきなのに放置していると、次のようなデメリットが生じます。
追徴課税や延滞税が発生
期限までに申告・納税をしなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
無申告加算税
申告しなかったことに対する罰則で、最大20%(悪質な場合は40%)の追加課税がされます。
延滞税
納付期限を過ぎていると、延滞税が発生。
年率は状況により異なりますが、長期間放置すると金額が大きくなります。
延滞税の税率は、延滞期間に応じて次のように分かれています(2024年現在の例です)
- 納期限の翌日から2か月以内:年 7.3% または 特例基準割合+1% のいずれか低い方
- 2か月を超える場合:年 14.6% または 特例基準割合+7.3% のいずれか低い方
※「特例基準割合」は日本銀行が定める基準割引率などをもとに毎年見直されます。
税務調査の対象になる
税務署は様々なデータを通じて情報を把握しています。
突然の調査が入ることもあり、過去数年分にさかのぼって申告を求められることもあります。
調査の結果、意図的な申告漏れや隠ぺい行為があった場合、脱税とみなされ、重加算税等や罰金懲役などの刑事罰に問われる可能性があります。
青色申告の取り消し
無申告が続くと、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
これにより、青色申告特別控除や、特典である専従者給与が必要経費として認められなくなってしまいます。
特に専従者の多い家族経営の場合は、税負担が大きく増加する恐れがあります。
社会的信用の低下
事業者であれば、取引先や金融機関との信頼関係に悪影響を及ぼすこともあります。
また、納税証明書や所得証明書が発行されず、住宅ローンや融資の審査に通らないなど生活面にも支障が生じるおそれがあります。
参考ブログ:税務調査の体験談 連絡から終了後までの基礎知識
ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495
確定申告していないことがバレる理由
税務調査
税務署は、税務調査の際に調査対象となった事業者や個人の申告内容を確認するだけでなく、その相手先と取引のあった他の関係者についても、同時に確認作業が行っています。
たとえば、あるフリーランス事業者が税務調査を受けた際、その人が報酬を支払っていた外注先や、逆に報酬を受け取っていたクライアントについても、税務署が関心を持つ可能性があります。
こうした関連先への調査や情報収集を通じて、申告漏れや収入の不一致が発見されることも少なくありません。
税務調査で得られた情報は、単なる参考資料にとどまらず、実際の調査や判断の中で「確度の高い情報」として重視されています。
そのため、取引先が税務調査を受けた場合、自分自身の申告状況が改めて注目されるリスクがあるという点も、十分に意識しておく必要があります。
支払調書の提出
税務署は、毎年全国の事業者から提出される膨大な数の支払調書をもとに、個人の収入状況を詳細にチェックしています。
そのため、報酬を受け取ったにもかかわらず確定申告をしていない場合、「無申告」が簡単に発覚してしまいます。
つまり、事業者が報酬の支払いを報告している一方で、受け取った側が何の申告もしていない場合、その不整合はすぐに浮き彫りになるのです。
「税務署にはバレていないだろう」と自己判断で申告を怠ることは、非常にリスクの高い行為であるといえます。
第三者からの情報提供やSNSの情報
税務署には、不正行為や無申告を匿名で通報できる制度があり、第三者からの情報提供によって収入が発覚することがあります。
この制度により、家族や知人、元同僚、取引先など第三者が「申告していない収入がある」「副業で高額の収入を得ているのに申告していない」などの情報を、本人に知られることなく税務署に提供することが可能です。
実際に、税務調査のきっかけとしてこうした通報情報が使われるケースは少なくないようです。
また、SNSなどで活動内容を発信している場合、実際の税務調査でその情報を税務署は意外に確認していることに驚かされることがあります。
金融機関の口座確認
税務署は、必要に応じて銀行口座の動きを確認しています。
収入が金融機関の口座に振り込まれている場合、入出金のパターンから無申告の疑いを持たれることがあります。
特に、海外送金が多い場合などは、調査の対象となる可能性が高まります。
申告することで得られるメリットも!
確定申告は「義務」ですが、実は正しく申告することでお金が戻ってくるケースもあります。
節税につながる
- 青色申告による65万円控除
- 経費の計上で所得を減らす
- 家族に所得分散するなどの工夫
しっかりと税制を理解すれば、合法的に節税することが可能です。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、配当控除などにより、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
融資・ローン審査に有利になる
確定申告書は、所得を証明する公式書類として銀行や信用機関で使用されます。
住宅ローンや事業融資にも必要なケースが多いため、毎年の申告は信用構築にもつながります。
よくある質問(Q&A)
少額の収入でも確定申告が必要?
→ はい、副業などで年間20万円超の収入がある場合は必要です。(住民税については20万円以下でも申告の必要があります)
Q. 過去数年分も今か確定申告できる?
→ できます。最大5年分の申告が可能で、還付も受けられる場合があります。
Q. 税金が払えないときは?
→ 分納・延納制度があります。まずは申告してから相談すれば対応してもらえます。
Q. 副業が会社にバレないようにするには?
→ 「住民税を自分で納付」にすれば会社には通知されません。
Q.オンラインだけで無申告状態を解決したいのですが?
→ 最近では全国対応としている事務所もありますが、個人的には面談をして資料を一緒に確認しながら進めたほうが良いと考えています。無申告の状態は申告書を提出して終わりではなく、その後の申告作業や税務調査の対応なども視野に検討する必要もあることから近場の無申告でも対応してくれる税理士事務所を探すことが良いでしょう。
まとめ 確定申告せずに先延ばしにすると危険
安易にばれないだろうと考えて確定申告をしていない人は想像以上に多いですが、そのまま放置していると、多額の税金・罰金が発生するリスクがあります。
一方で、正しく申告することで適切に節税出来たり、還付金を受けられたりといったメリットも豊富です。
確定申告はわからなければ、税務署に相談することも可能ですし、最近ではスマホでの申告(e-Tax)も簡単になってきています。
数年間も無申告なので相談に行けないという人は「税務調査や無申告」が得意な税理士事務所を探して依頼すると良いでしょう。
当税理士事務所でも過去数年分の無申告について対応を行っておりますのでお困りの方はご連絡ください。
無申告・期限後申告に関するお問合せ
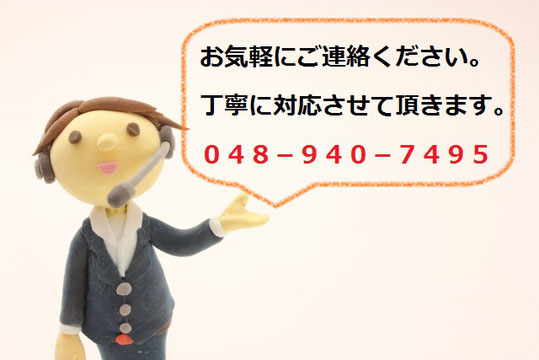
ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495
ひらい税理士事務所 代表税理士
埼玉県越谷市・草加市を中心とした近隣地域において、地域密着型の税理士として活動。
地域金融機関や関連他士業等とのネットワークを活かし、法人決算業務にとどまらず、資金繰り・融資支援、税務調査対応、相続税・資産税業務など、経営者の幅広いニーズに対応。これまで多くの税務調査に立ち会ってきた経験と、金融機関を意識した決算・申告書作成には定評があり、経営の安定と将来の発展を見据えた実践的なサポートを行っている。