「生計を一にする」に該当するかどうかは実務において非常に重要です。
税務調査立ち会いを行っていると、生計一であると考えたほうが納税者にとって良い場面もあれば、生計一と認定されてしまうと納税者にとって困る場面の両方に出くわします。

そこで、今回は我々専門家でも悩ましい「生計一」についての判断をご紹介します。この「生計を一にする」を正確に理解することにより税務上多くの場面で有利となります。
「生計を一にする」ということを要件とする規定は税法において非常に多くみられます。
3月ということもあり所得税に関連する規定を挙げてみると

- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 生計一親族に対する支払の必要経費不算入規定 など
多くの規定でこの「生計一」が要件となっています。
「生計一」の一般的な感覚としては”同じ釜の飯を食べている”といったところかと思います。これは、かなり的を得ているところかと思いますが、税法上はもう少し範囲を広くとらえています。
「生計一」の意味は法令上は明記されていませんが、通達により明記されています。関係通達としては以下のとおりです。
- 所得税法基本通達2-47
- 法人税法基本通達1-3-4
- 国税通則法基本通達46条関係
上記3つの通達は微妙な言い回しが違いますので簡単にまとめました。
所得税法基本通達
①同居していない親族であっても以下の場合には生計一とする
・勤務、修学、療養等の都合により同居していないが余暇には起居を共にすることが常例。
・常に生活費、学費、療養費等の送金が行われている。
②同居している場合には明らかに独立した生活を営んでいる場合を除き生計一とする。
法人税法基本通達
有無相助けて日常生活をの資を共通していることをいい、同居していることを要しない。
国税通則法基本通達
①有無相助けて日常生活の資を共通していること
②同居をしていないくても常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養していること
③同一家屋に起居していてもお互いに独立し、日常生活の資を共通にしていない親族は生計一ではない。
3つの通達から読み取れることは
(同居をしている場合)独立した生活をしている場合を除き、原則生計一と考える。
(別居の場合)仕送りをしている場合や金銭的な援助があるには生計一と考える。
しかし、ここで解釈が必要なことが出てきます。
「独立した生活」と「仕送りの金額基準」についてです。この定義については通達では明らかにされていません。
そのため「この定義に関する解釈」は過去の判例を読み、独自に解釈をしていく必要があります。
生計一の判断に重要な影響を及ぼす「独立した生活」とは?
「独立した生活」の定義について争われた事例は多くあります。
それらの事例から読み取れるキーポイントは以下の通りです。

- 玄関・台所・お風呂などを共有していたか
- 自由に往来が可能であったか
- 電気・水道・ガスのメーターは別であったか
- 敷地の地代・家賃の支払いの有無
- 食事は一緒にしていたか
- 国民健康保険の世帯はどのような形であったか
- 家計費の負担を行っていたか?(生活費のお財布は一緒であったか?)
- 不動産登記は別々になっているか
どれか一つに当てはまるからといって生計一であるとは言い切れず、上記のポイントを複合的に鑑み、生計一がどうか判断されています。
生計一の判断に重要な影響重要な影響「仕送りの金額基準」
「仕送りに関する金額基準」に関しては税法上は明確になっていないことはすでに述べました。
そのため、判例から類推することとなりますが、私が見た限り、残念ながら判例でも金額基準は明確になっていません。
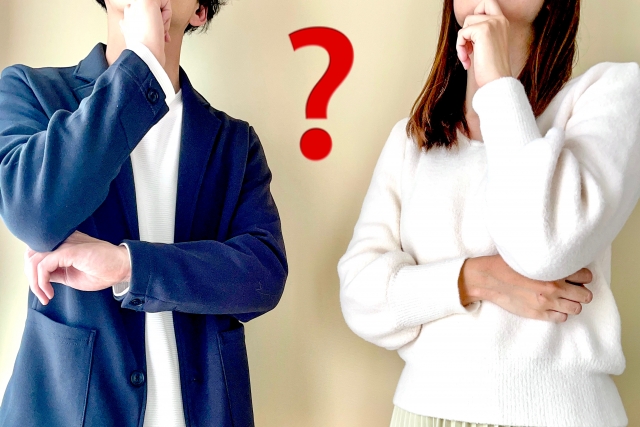
このような場合、この「仕送り」についての意味から税務調査では主張することも可能ではないかと個人的には思います。
結論(私見)
別居親族に関する生計一については仕送りがその判断に大きくかかわります。
ここで仕送りについて考えてみると、仕送りとは「生活・学業のために金品を贈ること(広辞苑)」ことです。仕送りをする意味としては生計維持を目的としていることはいうまでもないことです。
では「生計維持」とは何でしょうか?これはケースバイケースではないでしょうか。
個人によって状況は様々です。
学生、持病があり少しだけしか働くことができない親族(子供や親、兄弟)、介護施設に入らないと生活が成り立たない人など、それぞれ、通常生活を送るための必要資金は異なります。そのため、仕送りは、その人の収入により通常生活をおくることができない場合に必要となるわけです。
このような事情により金額的基準はないのです。
つまり、その仕送りが送金を受取った人にとって通常生活を送るためになくてはならないものであるか否かにより判断されるべきだと考えます。
送金を受けた人が自身の収入により、通常生活を維持できるのであれば仕送りは、単なるお小遣いでしかなく、仕送りとしての意味をなくす訳です。
よって、別居親族に対する仕送りがある場合には、その親族の収入等と仕送り金額を総合的に勘案し判断を行うことが必要であると考えられます。
「生計を一にする」ということを要件とする規定は税法において非常に多くみられます。
税金相談・税務調査に関するお問合せ

ひらい税理士事務所 越谷市蒲生寿町15-37 TEL:048-940-7495
ひらい税理士事務所 代表税理士
埼玉県越谷市・草加市を中心とした近隣地域において、地域密着型の税理士として活動。
地域金融機関や関連他士業等とのネットワークを活かし、法人決算業務にとどまらず、資金繰り・融資支援、税務調査対応、相続税・資産税業務など、経営者の幅広いニーズに対応。これまで多くの税務調査に立ち会ってきた経験と、金融機関を意識した決算・申告書作成には定評があり、経営の安定と将来の発展を見据えた実践的なサポートを行っている。
