
税理士という職業柄、多くの会社設立に関するお手伝いをしています。
関与させていただくタイミングは会社ごとにそれぞれ違いますが、最近多くなってきたと感じているのが、自分で会社設立手続きを終えて数か月が経過してから、顧問税理士を探すためにご相談にいらっしゃるケースです。
会社設立の手続きはネット検索やYouTubeなどで簡単に調べることが出来るようになってきているため、中には安易な会社設立手続きや設立後の重要な手続きが行われておらず、重大な問題が生じてしまっているケースもあります。
それでは法人設立について重要な問題が生じないようにするためにはどうしたら良いのでしょうか?
それは「失敗事例から学ぶこと」だと思います。
「会社設立に関する失敗」は、ちょっとした失敗から取返しのつかないような失敗まで実に様々で法人設立前の準備段階から法人設立後の手続き関係まで様々な時点で起こり得ます。
そこで以下では、他のサイトなどで紹介されている単なる会社設立に関する手続きについては触れず、税理士の私が実務で出会ってしまった失敗事例を中心に、会社設立前・会社設立時・会社設立後の3つのステージに分けて、『会社設立をする際に気を付けて頂きたい注意点』をご紹介します。

すべてを読んでいただくことにより法人設立の際の失敗は大幅に減ると思いますが、設立時の失敗談を多く記載していますのでボリュームがあります。
重要レベルを三段階にして★を付けています。時間がない方は星が多いものだけでもチェックしてみてください。
会社設立前に気にすべき注意点・検討しておきたい事項
会社設立については誰に相談すべきか? ★★
会社を作ろうと考えた場合、あなたはどのような専門家に相談しますか?
法人設立に関する専門家といえば司法書士、行政書士、税理士と3士業が一般的ですが、どの専門家に相談に行けば良いのか、多くの方が悩むようです。
原因はそれぞれの士業がどのような業務を得意としているかをあまり理解していないことにあると思います。

以下では会社設立について3士業が行う業務について比較してみます。
| 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | |
| 代行業務 | 法人設立手続きに関するスペシャリスト(定款作成・定款認証手続き・登記まですべて)を代行 | 法人設立手続きのうち定款作成・定款認証手続きを代行。ただし登記代行は不可。登記は本人が申請をする必要あり。(登記だけ司法書士へ依頼も) 法人設立後に許認可も視野に入れている場合には合わせて相談できる。 | 法人設立手続きは代行できないため提携士業に依頼している税理士が多い。法人設立後の手続き関係を代行 |
このように比較してみると、司法書士が会社設立に関する業務を代行してくれるのだから、まずは司法書士に相談しよう!!と考えると思いますが、おススメは税理士です。
理由は私が税理士だからということではなく、一番、会社設立後にどのような失敗談があるのかを見ているのが税理士だからです。
司法書士と行政書士は法人設立手続きのプロとして書類作成の代行は行ってくれますが、会社設立手続きを如何にお客さんの都合にあった形でスムーズに行うかということが最も重要なミッションになり設立後のことはほぼノータッチです。
しかし、税理士は会社設立後からが業務開始になりますので、会社設立後を見据えてどのような形の会社を作ればよいかをお客さんと一緒に考え、その姿を想像したうえで提携先の司法書士や行政書士と連携してサポートします。
各士業が何を業務としているかを明確に理解していないとなかなかわからない部分かもしれません。

会社設立を検討する場合には本当に会社設立が必要なのかも一緒に考えてくれる信頼出来そうな税理士に相談してみることをおススメします。
設立関係をよく手掛ける税理士は司法書士、行政書士、社会保険労務士など他士業とのパイプを必ずもっています。
そのため、会社の基本設計を税理士と一緒に検討したうえで、他士業を紹介してもらうことによりスムーズにご自身が希望する会社の形を作ることができます。
例えば、私の場合、会社の基本的な形をお客様と考えた後は、個人所有の物件を法人成りさせるような会社設立については司法書士さんを紹介しますが、建設業許認可を取得する場合や許可取得を目指すような場合には行政書士さんを紹介しています。
※士業にはそれぞれの領域があるため上手に使いわける必要があります。
【過去にあったヒヤリハット事例】
法人設立に伴い市の創業支援事業の窓口に行き、創業融資や補助金の相談をした際に中小企業診断士から、まずは司法書士のところに行きなさいと言われた。資本金の妥当額や社会保険などを一切考慮せずに定款の作成が行われていた。運よく認証前に来所されたため、急いで司法書士へ連絡をとってもらい定款の認証を中断。資本金の額や社会保険に関する再検討を行った。
→この事案は司法書士は登記のスペシャリストであるということだけしか理解せず、登記後の会社運営のこともよく理解していると思いこんでしまっていたことによるヒヤリハット事例でした。
会社設立をする目的は何でしょうか? ★★★
私の場合、会社設立をしたいという方と打ち合わせをする際に必ず法人成立の目的を聞くようにしています。
弊所に相談に来られる方に目的を聞いてみると以下3つに大別することが出来ます。
- 節税目的
- 法人でないと取引に制限がある(個人事業では取引してもらえない。
- 資産承継や資産拡大目的

節税目的
「節税」は法人化を検討する最も多い理由かと思います。
確かに税金だけを考えると得になるケースは多くあります。
しかし、社会保険・法人の維持費(税理士費用等)なども考えるとメリットが大きく出てくるケースは意外に少なく、設立後、こんなはずではなかったのに・・・ということも。
仮にあなたが、節税目的で法人成りするのであれば、税金だけではなく、社会保険の負担増や設立後の維持費用も含め、十分効果が望めるかどうかを検討し、法人を設立されることをお勧めします。
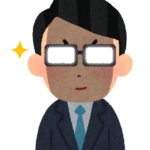
【補足】
法人成りを検討する際に税金と社会保険の軽減だけで考えると負担がほとんど変わらなかったり、法人成りをすることにより、むしろ負担が増加することもあります。多くの方がこの時点で考えることをやめてしまいます。
しかし、安易にそれだけを比較せず、支払う内容の変化にも目を向ける必要があります。
一般的には法人成りをすると税金が減る代わりに健康保険と厚生年金が増加します。
ここで重要なことは税金の減少の代わりに厚生年金保険料が増加という部分です。
国民年金被保険者から厚生年金被保険者に変わることにより多くの恩恵が得られます。
要件を満たすことにより、自分の老後は当然のこと、ご自身が死亡したときに残された大切な家族の生活を支えるために遺族厚生年金を受給できたり、障害を負い働けなくなったりしたときにも障害厚生年金を受け取れるようになります。
私的年金は、営業マンから不安をあおられ加入している方は多いですが、公的年金の有用性については自分自身で勉強しないと気が付かないため見落とされている部分かもしれません。
参考ブログ
法人でないと取引上の制限がある場合
比較的大きな企業を取引先としている個人事業主や最近では消費税のインボイス関係でよく聞く理由です。
取引上の制限がある場合には法人成りをすることにより、一般的には信用力が増加します。また、取引規模が大きくなるため個人保証の問題も非常に重要となってきます。
商売を大きくするためには法人成りは必須です。
上記の節税も踏まえ、有利な形で法人成りを進めましょう。
資産承継や資産拡大目的
近年の不動産投資ブームで多く頂く質問です。
不動産は移転コストが高いため、一定規模以上にする予定の方は早めに枠づくりのための法人設立を検討しておく必要があります。
特に個人の属性が高い方の場合には所得税の累進税率に注意する必要があるため、法人化はぜひ検討したいところです。


会社設立の目的を明確にし、その目的を達成する手段として法人設立が本当に必要かを検討することが必要です。
迷っている場合には、法人設立について一緒に考えてくれる税理士に相談しましょう。
参考ブログ
事業資金の目途をしっかり立てること ★★★
住宅ローンは頭金がほぼ無くても通ったのだから事業資金に関する融資も簡単に通るだろうなどと、事業性融資のことを甘く考えてしまっている人が多いです。
しかし、実際には事業性融資は住宅ローンのように甘くはありません。
そのため、事業を開始する前に、軌道にのるまでの必要資金は必ず計算しておく必要があります。

必要資金を計算したうえで十分に手持ちの資金で賄えるのであれば融資は不要ですが、足りないようであれば融資を開業前に検討しておきましょう。(融資手続き自体は事業開始後や法人設立後でないと出来ませんが、創業前だからこそ一歩立ち止まり、十分な準備をすることもできます。)
創業融資を受けるための準備
創業融資を受けるためには「創業するための準備が出来ているのか?」ということが問われます。
そんな当たり前のことを書くな!!と怒られそうですが、ここで言いたいことは「お金を借りるための準備」も含まります。
では、「お金を借りるための準備」とは何でしょうか?
それは金融機関にとって、「あなたが貸したお金をしっかり返してくれそうな人」に映っているかということです。(仮にあなたが人にお金を貸す場合でも最も重要視することだと思います。)
そして金融機関が創業時に「あなたが貸したお金を返してくれそうな人」かどうかを多くの経験則から以下のようなことにより判断しています。

判断1 融資したお金を返すことができるような事業内容か?
事業計画は妥当なのか?事業計画が妥当であれば、軌道にのったあとしっかり融資したお金が返ってくるほどの利益がでるのだろうか?
※判断材料:事業計画書の中身

判断2 事業に対する思い、計画性はどうだろう?
この人は創業するにあたり、どのくらい前から計画してきたのか?前から計画しているのであれば当然お金もそれに向けて貯めていて当然だ。事業に対する思い入れがなければ長続きもしないし、しっかり事前準備が出来ていない人にはお金は貸したくないなぁ・・・
※判断材料:自己資金と融資申し込み額のバランス

判断3 この人は約束を守れる人なのか?
いくら事業が上手くいっても、しっかりお金を返す約束を守ってくれる人なのだろうか?踏み倒したりしないか不安。過去にクレジットカードの支払などで約束を破っている人には貸したくないなぁ・・・。
※判断材料:CICなどで個人情報をチェック、支払遅延などがないか確認
上記の3つは起業前に準備しておくべきことです。問題があるようなら「お金を借りるための準備」が整っていない状況です。創業前だからこそ、一歩立ち止まり事業資金を貯めたり事業計画の練り直しなどの対策を行っておく必要があります。
創業融資はどこから融資を受けることがおススメ?
創業時の融資は日本政策金融公庫が行っている創業融資か、自治体・金融機関・信用保証協会が連携して提供している制度融資かの2つに大別されます。
そのうち、最も頼りになるのは日本政策金融公庫が行っている創業融資です。
日本政策金融公庫は国が100%出資している政府系金融機関であり、民間の金融機関の補完的位置付けとされていますが、民間金融機関では融資がしづらい創業期は特に頼りとなる存在です。
日本政策金融公庫で創業には、「新創業融資制度」「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」など、創業の際に利用できる融資制度がいくつかありますが、その中でも「新創業融資制度」は、特に人気の制度です。
「新創業融資制度」は、これから事業を始める方、又は事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象にしており、原則として無担保・無保証人で、最大3,000万円(そのうち運転資金は1,500万円)までの融資が可能となっています。
参考ブログ
会社設立時に気にすべき注意点
設立手続きは専門家?自分でやる? ★
会社設立に関する手続きについては、最近では専門家に頼まず、自分でやる方も多くなっています。
私が考えるメリットとデメリットを以下のようにまとめてみました。
| 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 自分でやる | |
| メリット | 会社設立に関する手続き(定款作成、認証代行、登記)をすべて代行してくれる。不動産の登記なども一緒に依頼することが可能 | 会社設立に関する手続き(定款作成、認証代行)を代行。登記は原則自身で行うため司法書士より費用が若干安いことが多い | 法人設立後のことを見越したアドバイスをもらえる。提携先の司法書士や行政書士に依頼。事務所によってはその後の顧問契約を締結することにより会社設立費用はゼロという事務所もある。 | 最近では弥生、マネーフォワード、Freeeなどがオンラインで簡単に法人設立手続きを行える仕組みをつくっている。(無料~数千円程度)※電子認証も対応している。 |
| デメリット | 費用がかかる。 | 費用がかかる。 法人登記は行政書士が提携している司法書士に依頼するか又自分で行う必要あり。 | 費用がかかる。 税理士自体は会社設立手続きは不可 顧問契約とセットの場合には法人設立後に税理士選択に支障をきたすことがある。 | よく調べないで安易に設立をしてしまうと重大な問題が発生してしまう可能性もある。 |

よく自分でやるより●万円お得などと記載しているホームページを見かけますが自分でやる場合については電子定款でないことを前提としており、しっかり費用が発生していることを理解したうえで専門家に依頼しましょう。(実際にはお得ではないということを理解しましょう)
法人設立に伴い資本金はいくらにしたら良いのか? ★★
「資本金をいくらにするば良いのか?」という質問は法人設立に関する相談で必ずといってよいほど多く頂く質問です。
状況により答えは変わってきますが、私の場合には以下の3つから選んでもらう場合が多いです。
| 資本金の額 | 理由 |
| 300万円 | 会社設立理由は様々ですが、大きな理由の一つに信用力の向上があげられます。 そのため資本金の額はあまりに少額の場合には逆に信用力を無くします。 今は作れませんが有限会社の最低資本金は300万円でした。 一定額以上なければ昔は会社作れなかったことが今の世の中でも会社形態に一定の信用力があることにつながっているわけです。 |
| 500万円 | 会社成立後に許認可を取る場合には資本金(純資産)の要件があるケースも。 例えば建設業の許認可を取る場合には500万円が基準となります。 |
| 500~1000万円未満 | 資本金が1千万円以上の場合には消費税の納税義務判定が異なります。 また、1千万円超となった場合には均等割りの金額が増加します。 |

最近は最低資本金も撤廃されているため、資本金はいくらでも良くなりました。
でも、あまりに低い資本金にしてしまった場合、融資や今後の取引にも影響が生じる場合もあることに注意が必要です。
実際に金融機関の融資担当課長や顧問先の社長とお話ししたことをご紹介します。

資本金の額があまりに少ない会社に対しては融資がしづらいです。
理由としては、事業に対する真剣度合が感じられないこと、すぐに債務超過に陥るからです。

新規取引先を選ぶ際、信用調査は欠かせません。
新規取引先には決算書を提出してもらい全部事項証明書(謄本)を取り寄せて財務状況をチェックします。
債務超過の会社とは基本的には新規取引はしません。
また、新規法人などの場合には資本金があまりに低い会社はすぐに債務超過になるため取引はしづらいですね。

創業融資を受ける場合に最も重要となるのは自己資金です。
個人事業をしていた場合には実績があるため、融資時に実績をアピールができますが、新規に事業を始める場合には、前職での経験のほか、自己資金が重要な判定要素になります。
例えば、日本政策金融公庫の新創業融資における自己資金要件は10分の1以上が目安とされていますが実際の肌感覚としては3分の1以上が必要です。
金融機関の担当者から断られた理由を聞いてみると「資本金の額(自己資金)が・・・」といったことが過去に何度もありました。
株主はだれにすれば良いのか? ★★★
株式会社の場合、会社の重要事項は株主総会で決定されます。
合同会社の場合には社員総会です。
株主は誰がなるのかは非常に重要です。
株式会社の場合、役員の選任、役員報酬の決定、配当金の金額決定、会社の定款変更、合併や解散など会社の重要事項はすべて株主(株主総会)が決定します。
代表取締役がすべての株式を保有しているような場合には株主総会は形骸化しているケースが多いですが、株主が複数人いるような場合には注意が必要になってきます。
株主を普段から意識している中小企業は少ないですが、関係性が悪化した場合には会社が機能不全に陥る可能性があり、むやみに株主を増やすことは控えたほうがよいでしょう。

代表取締役が主に業務を行う人なのに過半数の株式を保有していない場合、会社の意思決定に問題が生じる可能性があると金融機関から見られてしまうこともあります。
複数人が株主となる場合には出資比率に注意が必要です。
合同会社の場合には社員数に注意しましょう。
代表取締役、業務執行役員を誰にするのか? ★★★
代表取締役や業務執行役員を誰にするのか?
家族経営の会社の場合、実質的な経営者以外が名目上の代表取締役や業務執行役員になることがあります。
これは絶対NGです!!


社長を奥さんにするケースが多いですが、このことが問題になったことは1度や2度ではありません。そのほかにも過去問題になったケースをご紹介します。
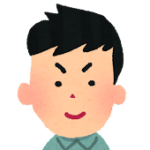
会社で副業が禁止のため、妻を代表取締役にしたところ、金融機関から口座開設を断られました・・・

過去にクレカで遅延があり、住宅ローンの際に苦労したので、名目上、妻を代表者にしたところ、実質的な事業者を確認され融資を断られました・・・

合同会社にて奥さんも業務執行役員に入れ役員報酬を支払ったため、奥さんが社会保険の扶養から外れてしまった。

役員は多いほうが拍がついてよいだろうと思い、知人にも入ってもらっていた会社。条件も悪くないのに金融機関から融資を断られた・・・・。
担当者に内緒で訳を聞いてみたところ、実は役員に入ってもらった知人の信用状況に問題あった・・・・・。
役員には誰を入れるべき?任期は? ★★★
役員の人選
実績がある人を引っ張りこむために名前だけでも役員になってもらおうと考える起業家も多いようです。しかし、名前だけの役員が原因で融資を断られるケースも存在します。
その役員が過去に金融事故を起こしているような場合には要注意です。
役員の任期
平成18年の会社法改正により役員の任期は10年まで伸ばせるようになりました。
10年にするメリットは登記の手間や費用を抑えらえることです。
しかし、デメリットもあります。
例えば、第三者を役員に入れ任期を10年にすると当然ながらその方は原則10年間は役員です。
しかし、10年の間に経営状況やその方との関係性が変化していくのはごく自然のことです。
良い関係性が維持出来ているのであれば問題ないのですが、関係性が悪化し、関係を解消しようとしたときに任期期間中であれば解任理由に合理性が認められないときには損害賠償請求をされるリスクがあります。
手間と費用はかかってしまいますが、2年間の任期であれば、上記のリスクは最小限に抑えることが出来ます。
安易な人選により、損害賠償までは行かなかったものの一歩手前まで関係がこじれてしまったことは一度や二度ではありません。役員の人選、任期ともよく検討する必要があります。
会社形態 株式会社か?合同会社か? ★★
近年では、会社設立というと株式会社か合同会社の設立であることがほとんどです。(有限会社は作れません)
では、設立形態として一体どちらの形態で設立すべきなのか?
これについて私見を述べていきたいと思います。
※以下は個人的意見です。

なぜか勧められる合同会社
インターネットで検索してみると株式会社と合同会社の比較が掲載されています。
法律的には様々な違いがあり、上手に使い分ける必要があると思いますが、実務上、選択基準となってしまっているのは、10万円ほど安くなる設立費用です。
司法書士さんや行政書士さんが設立費用が安くなることを理由に安易に合同会社を勧めているケースが散見しています。
私が株式会社を勧める理由
私は法人形態の相談をされた場合、株式会社を勧めています。
合同会社も立派な法人です。
しかし、歴史も浅く、知名度は株式会社の足元にも及びません。
合同会社のほうが安く設立できることは確かですが、10万円程度安くなるだけです。
税負担も考慮すれば持ち出しは7万円程度です。
これから事業を大きくして行こうと考える場合、最も大事なのは信用力です。
その信用力を7万円程度で判断される場合もあることを十分考慮すべきです。

実務上、事業者や金融機関から合同会社に対してマイナスイメージを聞くことは意外に多いです。
合同会社であっても立派に会社経営をしている方が大半だと思いますが、以下のような話も実際にはあることを会社設立前に知っておくことが重要です。
(合同会社の方、すみません・・・・)

合同会社の場合、融資をした後に問題が生じるケースが株式会社よりも多い。また、最近では設立費用の安さからマネーロンダリングに使われるのも合同会社だったりするので新規取引を行う際は少し抵抗があります。

合同会社は会社設立のための登記費用を支払うことが難しいような資金が苦しい会社が多いイメージがある。

合同会社は出資比率に関係なく1人1票の議決権をもっていることから出資者同士の意見対立が起きたり、利益分配でトラブルに発展することもあります。
また、定款をいい加減に作成されていると、社員が死亡したときに解散リスクもあります。
会社設立にかかる登録免許税の軽減 ★
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が対象です。
市区町村が地域の支援機関(商工会等)と連携して実施される「特定創業支援等事業」の支援を受けると、会社設立にかかる登録免許税を半額にすることができます。
この支援事業の受講を修了すると、自治体から「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付されます。
この証明書を法務局に提出することで会社設立にかかる登録免許税が半額になります。
更に、設立時の登録免許税の減免だけでなく、融資の際に利率が優遇されたり、自己資金要件等が緩和されるなどのメリットもあります。
ただし、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を発行してもらうには、要件があり、市区町村によるとは思いますが、手間と時間を要します。
例えば越谷市の場合には以下のような条件を満たす必要があります。
「1回1時間程度の個別相談(講義)を、1か月以上にわたり、4回以上かつ1年以内に受け、4分野(経営・財務・人材育成・販路開拓)の知識が身についたと認められる方が対象」

スタートアップの方にとっては知識の習得にもなるためおススメです。
通常、法人設立のための登記免許税は、株式会社なら15万円、合同会社なら6万円かかりますので半額となると株式会社は7.5万円、合同会社なら3万円となります。
起業までの時間が十分ある場合には起業前に行っておくと良いでしょう。
参考ブログ
事業年度はいつにすべきか ★
個人事業者の場合、1月1日から12月31日までが1事業年度とされ、1事業年度における所得を計算して2月15日から3月15日までに確定申告を行います。
しかし、法人の場合には会計期間を自由に定款で定めて決算期を決めることが出来ます。
自由に決めて良いと言わると意外に困る人が多いのではないでしょうか?
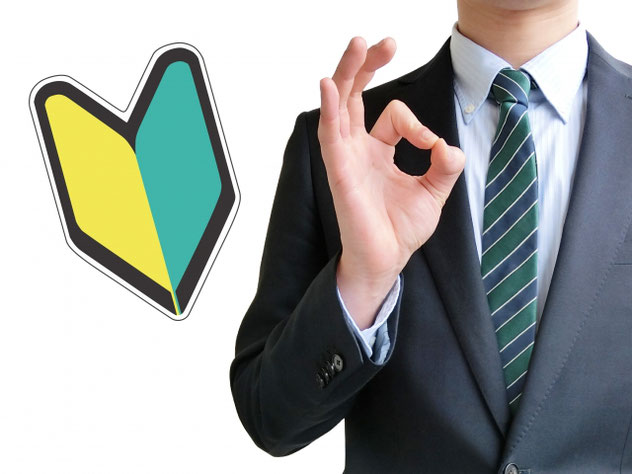
実際の法人設立時には以下のようなことを判断材料として決算期を決める人が多いです。
| 消費税の納税義務 | インボイス導入により今後は少なくなると思われますが、納税義務の免除期間が最大になるように1年目が12カ月取れるように設定します。 ※当面は2割特例も使えるため有効な考えです。 |
| 税理士報酬 | 法人設立後は税理士と顧問契約を結ぶ場合が多いと思いますが、事務所によっては繁忙期は報酬加算を行ったり、場合によっては業務を断られる場合もあります。 ※税理士事務所の繁忙期(★5つがマックス) 1~3月 ★★★★★ 法定調書提出や個人の確定申告のためものすごく忙しい。 4月 ★★★ 確定申告時期に出来なかった業務などの対応 5月 ★★★★ 3月決算法人(5月申告)が多いためすごく忙しい 6月 ★★ 納期の特例で外出が多い。 7月 ★ 比較的ゆとりがある時期。 8月 ★★ 税理士試験やお盆休みもあるため実働日が短い 9月~10月 ★★~★★★★ 税務調査が多い年度は忙しい。年により異なる。 12月 ★★★★★ 年末調整の時期のためすごく忙しい 一般的な事務所であれば6月~8月は繁忙期でないことが多いです。 逆に避けたほうが良い決算月は12月と1月です。 12月決算は決算月の12月が年末調整時期。申告月の2月は確定申告期間という税理士にとっては最も回避したい決算月となります。(個人から法人成りの場合、キリが良いのでこのケースが結構多めですが・・・) 1月決算も決算月の1月は法定調書等や確定申告の準備期間。申告月の3月は確定申告時期となるため、一般的な税理士事務所で1年を通して一番の繁忙期と重なり、税理士事務所にとっては非常に対応が難しい時期といえます。 ただし、事務所により業務の偏りはそれぞれのため、一番確実なのは依頼しようと考えてる税理士事務所に設立前に相談することが良いでしょう。 ※設立後に相談にいった場合、決算期を理由に繁忙期加算があったり、業務受任自体を断らることもあるため依頼したい税理士がいる場合には必ず設立前に相談に行きましょう。 |
| 売上の多い月を気にする | 売上が多く上がる月が事業年度の前半にくるように決算月の設定を行う場合があります。そうすることにより決算予測を行う際にブレが少なくて済み、決算対策を講じやすくなります。 決算作業は時間がかかるため、自社の繁忙期を避けたほうが事務作業に時間もかけられます。 |

設立当初、あまり深く考えずに事業年度設定をしている場合には、後日定款の変更により事業年度を変更することが出来ます。
ただし、消費税の納税義務などにも影響することがあるため、事業年度変更の影響を事前に検討しておく必要です。
【補足】会計ソフトにまつわるちょっとした裏話

最近は様々な会計ソフトが発売されていますが、注意すべきは利用している会計ソフトによっては税理士が受任拒否することがあるということです。
特に依頼したい税理士が決まっているようであれば、導入前に相談をしておくほうが無難です。
依頼したい税理士が決まっていない場合であれば、多くの税理士が使っている弥生会計などにしておけば会計ソフトを理由に依頼を断られることがほぼ無くなると思います。
※ここでは詳しく書けませんが多くの税理士が嫌っているものも存在します・・・・。
地域検索でサポーターとして登録している税理士がどれくらいいるのか確認し、サポートする税理士の人数が少ないものは避けておいたほうが無難です。
本店所在地はどこでもよい? ★★
本店所在地を社長の自宅であったり、親の自宅としている方が多いですが、本店を安易に決めてしまい、後悔するケースもあります。
実務でよくある失敗は口座開設、融資、補助金についてです。
口座開設・融資
個人口座を開く場合にはそれほど大変ではありませんが、法人口座を開く場合には本店所在地によっては断られることがあります。
例えば、最近流行りのバーチャルオフィス。
確かに便利ですが、事業実態が確認できないということで難色を示す金融機関が多いです。
法人口座を開く場合には所在地に確認しに来ますので、その際、本当に事業を行っている会社なのか疑問を持たれてしまいます。
また、中小企業がお付き合いをしたい信用金庫などは営業エリアの問題も影響するため注意が必要です。
補助金
財源の問題で一般的には都市部のほうが制度は充実しています。
コロナ禍に伴う都道府県や市区町村の独自の給付は大きく各地で異なっていたことを見れば一目瞭然です。
このような違いはコロナ禍ではない平常時でも常に存在します。本店所在地をどこにするかは商売をしていくうえで極めて重要な事項です。
そのため、慎重に決定すべき事項ですが、甲乙つけ難い場合には各候補地の中小企業に対する公的施策を比較検討してみることも一案です。

私の事務所は越谷市と草加市の境ぐらいに位置しています。
地域の補助金は申請期間が短いため、よく越谷市と草加市の補助金の比較をしていますが、過去の補助金として以下のような違いがありました。
※隣接している市区町村でも市区町村の方針により内容が大きく異なります。

創業に関する補助金
越谷市は私が知る限り毎年予算がついています。
しかし、お隣の草加市は3~4年前は予算がついていましたがが最近は予算がついていません。
ちなみに令和5年の越谷市の創業補助金は6/19~6/30が応募期間。
家賃や広告宣伝などにかかった金額の1/2を100万円を上限として補助してくれます。

昨年のガソリン価格高騰に対する補助金
要件をみていた限り、草加市のほうが対応が早く対象が広範囲で手厚いイメージでした。。。。。

R5年度に行われた貨物自動車運送事業を行っている方への補助金について私の事務所がある越谷市周辺について調べた限りでは
越谷市:1台あたりにつき補助金あり
草加市:燃料の使用量に応じた補助金あり
吉川市:3回ぐらいにわたり運送業以外でも燃料高騰に対する補助金あり。
というように市町村により随分と違いがありました。
参考ブログ
社会保険は強制加入。国保組合の継続加入も比較検討しておく ★★
法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法令により健康保険・厚生年金が強制適用となります。
ただし、健康保険については個人事業主時代に国民健康保険組合に加入している場合、組合によっては年金事務所で健康保険の「適用除外承認」を受ければ、国保組合に継続して加入することができるケースがあります。
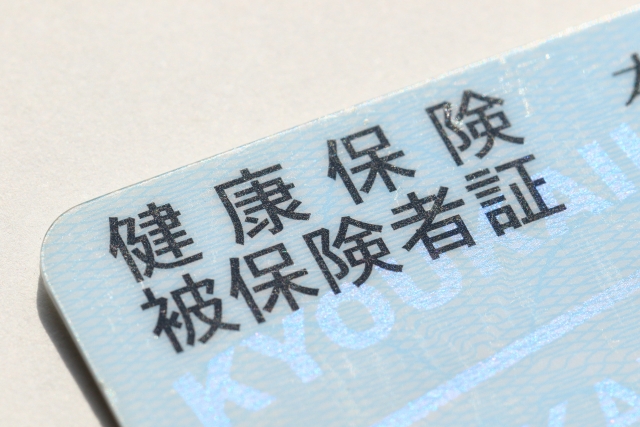
健康保険は役員報酬の増額と比例して高額になっていきますので、国保組合での国民健康保険の負担額と政府管掌の健康保険とを比較検討しておきましょう。
参考ブログ
個人で建設業を営んでいる人が入れる国民健康保険組合について比較してみた。

法人設立を検討する際に税負担の軽減を目的にする場合が非常に多いですが、社会保険も考慮すると税金の代わりに社会保険が増加するため、税金と社会保険をトータルで考えるとそれほど手残りは変わらないことが多いです。
しかし、大きく異なること税金の代わりに社会保険(年金)を支払うことになる点です。
年金が国民年金から厚生年金に代わることにより将来もらえる年金が増えます。また、仮に自分が死亡した場合も家族は遺族基礎年金だけでなく遺族厚生年金の受給も可能になる場合もあります。税金と社会保険。同じように国支払うものですがその効果は全く異なります。
目に見えるお金だけではなく、その後の効果も考え有利不利を判断しましょう。

個人事業主から法人成りした場合、年金は国民年金から厚生年金となります。
法人成りの狙いの一つとして奥さんを3号被保険者にして社会保険負担を軽減することを検討しますが、第三号被保険者になる届出を失念していることがあります。
特に法人成り後に国保組合に継続加入をするケースでは健康保険被保険者適用除外承認申請手続きもあることから注意が必要です。
個人事業主時代は奥さんの国民年金も普通に支払ってきたためそんなもんかと思ってしまっていることも原因の一つのようです。
会社設立後に気にすべき注意点
青色申告の届出は期限に注意が必要 ★★★
法人設立後に行う税務上の届出で最も大切な届出が「青色申告の承認申請書」です。
青色申告の場合、繰越欠損金を10年間繰り越すことができたり、各種の特別償却や税額控除などの税金上のメリットがたくさんあります。
会社設立後3カ月以内か最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに所轄税務署長へ忘れずに提出しましょう。
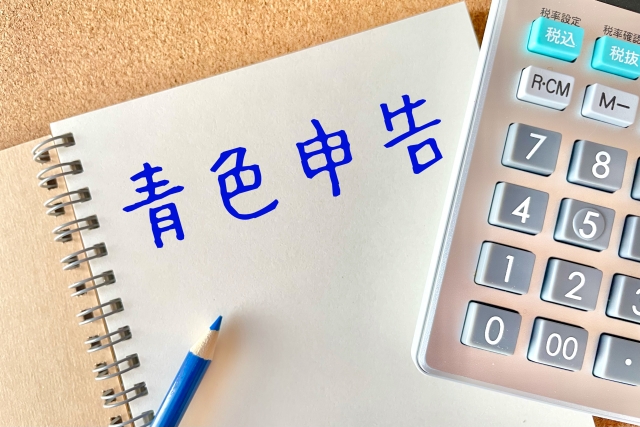

法人設立1期目は会社設立費用や事業が思惑通りにいかずに損失が発生することが多いのですが、この「青色申告の承認申請書」の提出を失念してしまうと損失を翌期以降に繰り越すことができなくなります。
法人設立に伴って税務署などに提出する書類は様々ですが絶対に忘れてはいけない書類です。
役員報酬は3カ月以内に決めた金額で固定する必要あり ★★★
法人設立をした場合、役員の給与(役員報酬)を早めに決める必要があります。
役員報酬は会計期間開始から3カ月以内に決定し、次の定時株主総会まで原則として変更することが出来ません。(定期同額給与)
一度決めた役員報酬を何度も変更してしまう人がいますが、変更前後の差額分が税金計算上の経費にならなくため絶対にやめましょう。

第1期は特に利益の額が読みにくいため、役員報酬の決定が遅れがちになりやすいですが、3カ月以内に必ず決定しましょう。

役員報酬の金額は大きく会社利益に影響します。また、社会保険の負担額にも直結する話ですのでしっかり検討しなければならない重要事項です。
社会保険の加入について ★★
法人設立をした場合、社会保険は強制加入となります。
原則として健康保険と厚生年金などの支払いが生じます。保険料の総額は個人負担と法人負担を合わせると給与の約30%くらいになり、個人事業主が支払う保険料より負担が重くなることが多いです。
年金については国民年金から厚生年金へと強制移行となりますが、健康保険については国保組合の移行が可能な場合があるのは前述した通りです。しかし、移行のタイミングは最初の給料を支払う前でないと移行不可となる組合があるようです。
移行を検討する方は事前に国保組合に話を通しておき、上記の役員報酬の決定タイミングと合わせ手続きの流れを考えておく必要があります。
個人事業主から法人成りを行う場合の資産承継・借入金の承継 ★★★
個人事業主が法人成りをする際に必ずといってよいほど問題になるのが個人事業主時代からの借入と事業用資産の引き継ぎです。
特に多額の金額を融資されている場合には法人成りを再検討したほうが良いぐらいの大きな問題になります。

個人事業主時代の事業用資産の引き継ぎ
個人名義の事業用設備や車両などを法人名義へ変更して使用したいと考える場合は多いと思います。
このような場合、本来は時価で個人から法人へ譲渡する必要があります。
ここで気を付けるべきことは時価と帳簿価格の差額は個人の譲渡所得(総合)となるということです。
法人成りをした年の個人の確定申告を行う際には忘れずに申告を行う必要があります。
また、事業用資産を譲渡した年度が消費税の納税義務者に該当する場合には消費税の申告も行う必要があります。
※仮に譲渡をしなくても消費税法上は「みなし譲渡」に該当することになるため注意が必要です。
参考:個人事業者が事業を廃止した場合(国税庁HP)
消費税の課税事業者に該当する個人事業者が事業を廃止した場合、その廃止の日の属する課税期間に係る消費税の申告が必要です。
また、個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費または使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。
この場合、当該事業を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm)
個人事業主時代の借入金を引き継ぐ場合
個人で事業を行っていると、個人名義で金融機関から融資を受けている場合があります。
このような場合の融資は事業資金として融資を受けていることが多く、法人成りをした後、金融機関から融資契約を個人から法人へ変更してほしいと依頼があります。
金融機関としては事業資金として融資を行っている以上、事業を行わなくなった個人へ貸し付けたままだと資金使途的に問題が生じるためです。このことは金融機関からしてみれば至極当然の話ですが、税務的には大きな問題が生じる場合があります。
個人の借入を法人が引き継ぐことになった場合、法人は融資を引き継ぐ代わりに、その負担することになった融資に相当する金額を個人から返済してもらう必要があります。
個人に資金があれば問題ないのですが返済することが難しい場合が多く、役員貸付金として処理せざるを得ないことが多々あります。
このことを失念していると個人としては法人から経済的利益(役員賞与)を受けたものとみなされ、多額の税負担が生じる可能性がありますので注意が必要です。

法人成りをする際、個人事業主時代の融資を法人へ引き継ぐことは多々あります。
金融機関も上記のようなことを説明すると付け替えが出来なくなってしまうため、詳しく説明されることが少なく法人成りをした数年後の税務調査で問題が生じるケースがあります。
役員貸付金が多額にあると融資を受けるうえで問題となることもあるため
事業資産の引き継ぎと合わせて融資の付け替えを上手に処理することが重要となってきます。

法人成りを検討する段階で金融機関から個人が融資を受けている場合はよくあるとですが、事業規模はすでに法人成りをしている企業に比べて小規模なことが多く、金融機関の担当者も経験が浅い方が対応していることが多いため、法人成り後の資金の付け替えまで頭が回っていないことがほとんどです。
付き合いがある信用金庫から法人成りした数カ月後にどう対応してよいか相談されることも多く、実務上、頻繁に問題になっています。
個人事業主時代の確定申告にも関係してくることもあるため、法人成りを行う前から検討したいところです。
参考ブログ
廃業事業年度の個人確定申告 ★★
個人から法人成りをする場合には、事業廃止に伴う手続き(廃業届・青色申告の取り消し・給与支払事務所廃止)と1月1日から事業廃止日までの期間について確定申告を行う必要があります。
事業廃止年度の確定申告は通常の確定申告と違い、以下のような特殊論点が出てきます。
法人成りの際は個人事業主時代の税務調査が行われるタイミングになることも多いため誤りがないように以下のような特殊論点に注意して確定申告を行いましょう。
| 棚卸の引継ぎ | 棚卸資産を法人が引き継いだ場合には売上高に引き継いだ譲渡対価を加算する必要があります。 譲渡対価は通常の販売価額の70%以上として著しく低い価格に該当しないように注意が必要です。 |
| 事業資産の引き継ぎ | 個人が保有する事業用資産を法人へ売却した場合にも収入として計上する必要があります。 一括償却資産や少額減価償却資産の場合には事業所得に該当します。 その他の事業用資産については「譲渡所得に該当」します。 時価の1/2未満を譲渡対価としてしまうと「みなし譲渡」に該当することになるため注意が必要です。また、消費税の計算上、よく漏れてしまうため忘れないようにしましょう。 |
| 減価償却の計算 | 減価償却資産については事業廃止日までの月数按分をする必要があります。 ただし、一括償却資産については取得価額のうち必要経費に算入されていない部分はすべて必要経費に算入します。 |
| 事業税 | 事業税は前年の事業所得に課税されます。 年の中途で法人成りをした場合、事業廃止後の翌年に納付を行うことになります。 そのため、見込納付額計算を行い必要経費算入を行います。 忘れないように注意しましょう。 |
| 消費税 | 消費税は原則として支払った際に必要経費に算入されます。 廃業年度に関する消費税納付は廃業年度の翌年に納付を行うこととなるため、 廃業年度の確定申告時に未払計上を行い必要経費に算入する必要があります。 忘れないように注意しましよう。 |
| 青色申告特別控除 | 青色申告特別控除額は月数按分は不要です。 |
| 法人設立費用 | 法人設立に関する費用は個人の確定申告における必要経費にはなりません。 法人の繰延資産(創立費)として処理します。 |
参考ブログ
金融機関選びで失敗 ★★
会社設立が終わるとまずやることは銀行口座を開くことです。
銀行口座がないと商売ができません。この際、重要になるのが金融機関選びです。
よく、脱サラした方が、いきなりメガバンクで口座を作ろうとしますが、明らかに間違った行動といえるでしょう。
便利というだけで選択せずに、事業開始後の融資についても検討しておき、身の丈にあった金融機関を選択することが重要です。
金融機関の種類と特徴は以下の通りです。
| 金融機関の種類 | 会社の年商イメージ | 特徴 |
| 都市銀行 | 数十億以上 | みずほ、三井住友、三菱UFJ、りそなの4行。多くの人にとって馴染みがあります。 ただし、取引相手として考えているのは大企業~優良中小企業です。 中小零細企業のしかも創業間もない会社はまず相手にしてくれないでしょう。 (最近では口座開設すら難しいこともあります。) |
| 地方銀行 | 1億以上になったら検討 | 都道府県単位と近隣他県にも跨って営業をしています。一般的には都市銀よりも規模が小さい企業をメインの取引先としていますが、都市銀がない少ない地方都市では都市銀の代わりを担っています。 |
| 信用金庫 | 1億円未満 | 地域に根差した営業をしています。営業エリアも地方銀行に比べ狭く、地方銀行よりも更に小さな企業や個人を取引先としています。ただし、金利は地方銀行よりも一般的には高めと言われています。 |
| 政府系金融機関 | 年商は関係なし | 有名どころでいうと日本政策金融公庫です。日本政策金融公庫は民間銀行を補完する役割を担っていますが、預金機能はありません。 |
| ネットバンク | 年商は関係なし | GMOあおぞらネット銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行などがあります。ネット銀行のメリットは口座開設がしやすく、振込手数料が安く、便利である点です。デメリットとしては融資審査が厳しいことがあげられます。 |

金融機関選びはその後の商売にも影響するほど重要な問題です。
まずはネットバンクと周辺の金融機関を調べてみましょう。
普段気にしていないだけで意外にも多くの金融機関があります。
そのうえで、どの金融機関とお付き合いをしていこうか検討しましょう。
顧問税理士が決まっていれば、地域の金融機関でおススメの金融機関を紹介してくれることもあります。
参考ブログ
税理士選びで失敗 ★★
最後に、税理士として多くのお客様を見ている中で感じていることです。
最近では税理士と検索すると実に多くの事務所のホームページを見るとことができます。
そして、様々な特色をもった税理士がいる中で税理士選びに失敗してしまう方が一定数います。
以下では、どうすれば税理士選びに失敗しないか私個人の意見を書いてみました。

税理士って何してくれる人?
税理士選びに失敗する人の特徴は「税理士はどんなことをする人なのか?」ということをしっかり理解していない場合が多いです。
例えば、私の事務所でサポートしている内容としては以下のような業務があります。(一般的な税理士事務所であればそれほど大きく変わらないと思います。)
| 通常の業務 | 臨時業務 |
| ・会計記帳や決算書の作成 ・法人決算申告(税務署・県税・市役所への申告) ・年末調整・法定調書・償却資産税申告 ・納期の特例対応 ・税務調査対応や税務署からの問い合わせ対応 ・相続税申告や株価対策 ・個人の確定申告(顧問先の社長や親族) ・決算予測や決算対策 | ・補助金や助成金の申請サポート ・税理士だけで対応出来ない問題について他士業の紹介 (社保、労務、登記、法務、許認可など) ・金融機関の紹介、融資サポート ・企業防衛のための保険見直し ・新規事業に対する税務リスク検証 ・法人成りについての検討 ・経営上の問題に対する打ち合わせ など。 |
通常業務については会社経営をしていればどの会社でも必要なこと、臨時業務については契約書などの業務範囲には書いていませんが問題が生じた際の解決策や未来に向けた対応を一緒に考えていくような業務です。
税理士の上手な利用方法を考えてみる
中小零細企業の場合はヒト・モノ・カネがなく、経営問題やお金の問題について相談できるような優秀な従業員の獲得はなかなか望めません。
そんな状況で、月数万円程度で自分が行う意思決定について、同じ経営者として違った目線で意見を言ってくれる税理士は貴重な存在となるはずです。
一定レベル以上の税理士と付き合いがある中小企業の経営者は「税理士をお金まわりのことを相談できる相手」と捉え、上手に税理士を利用しながら意思決定を行っています。
それにも関わらず「激安」事務所を一生懸命探し、コロコロと変わる実務経験が浅い担当者に限られた作業だけしかお願い出来ない状況を自ら作りだしてしまっている経営者がいますが、非常にもったいないと思います。
お金の管理について絶対の自信があり、限られた面倒な作業だけをお願いできればOKと割り切って考えている人は「激安事務所」で問題ないと思いますが、苦手な人ほど通常の税理士事務所をしっかり選別して自分にあった税理士を選ぶことが重要となります。(実際にはお金の管理が得意な人ほど税理士を上手に使い、苦手な人ほど上手く使えておらず、ずっとお金の苦労をしていることが多いですが・・・・)

税理士選びに失敗すると、税務調査のリスクや融資判断にも影響してきます。
いずれも会社の土台を揺るがしかねない重要な問題です。
お金の管理に自信がない人ほどしっかりとサポートしてもらえる税理士事務所に依頼することを強くおススメします。

税理士は地域密着型のビジネスのため、顧客は近隣の会社が多くなります。
そのため、上記の述べたような市区町村独自の補助金や融資制度などの情報も持っていることが多いため、近隣の事務所を選ぶ方が良いのではと個人的には思います。
参考ブログ

